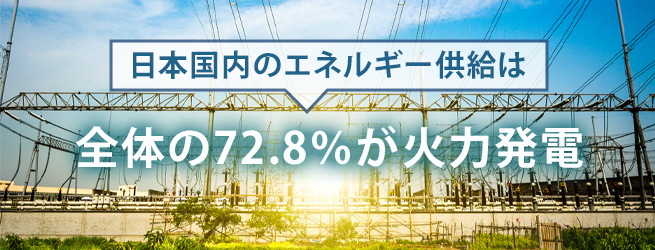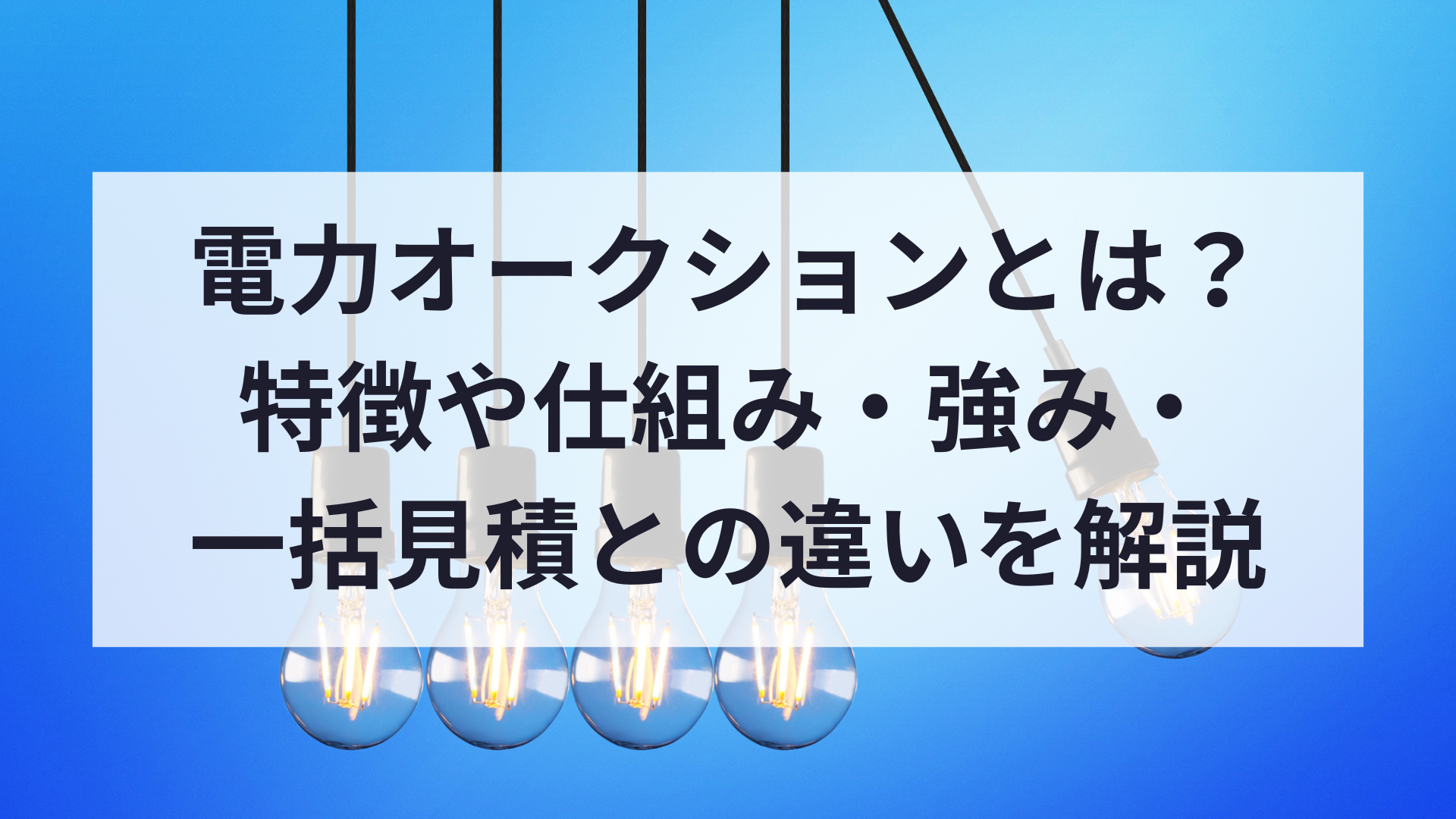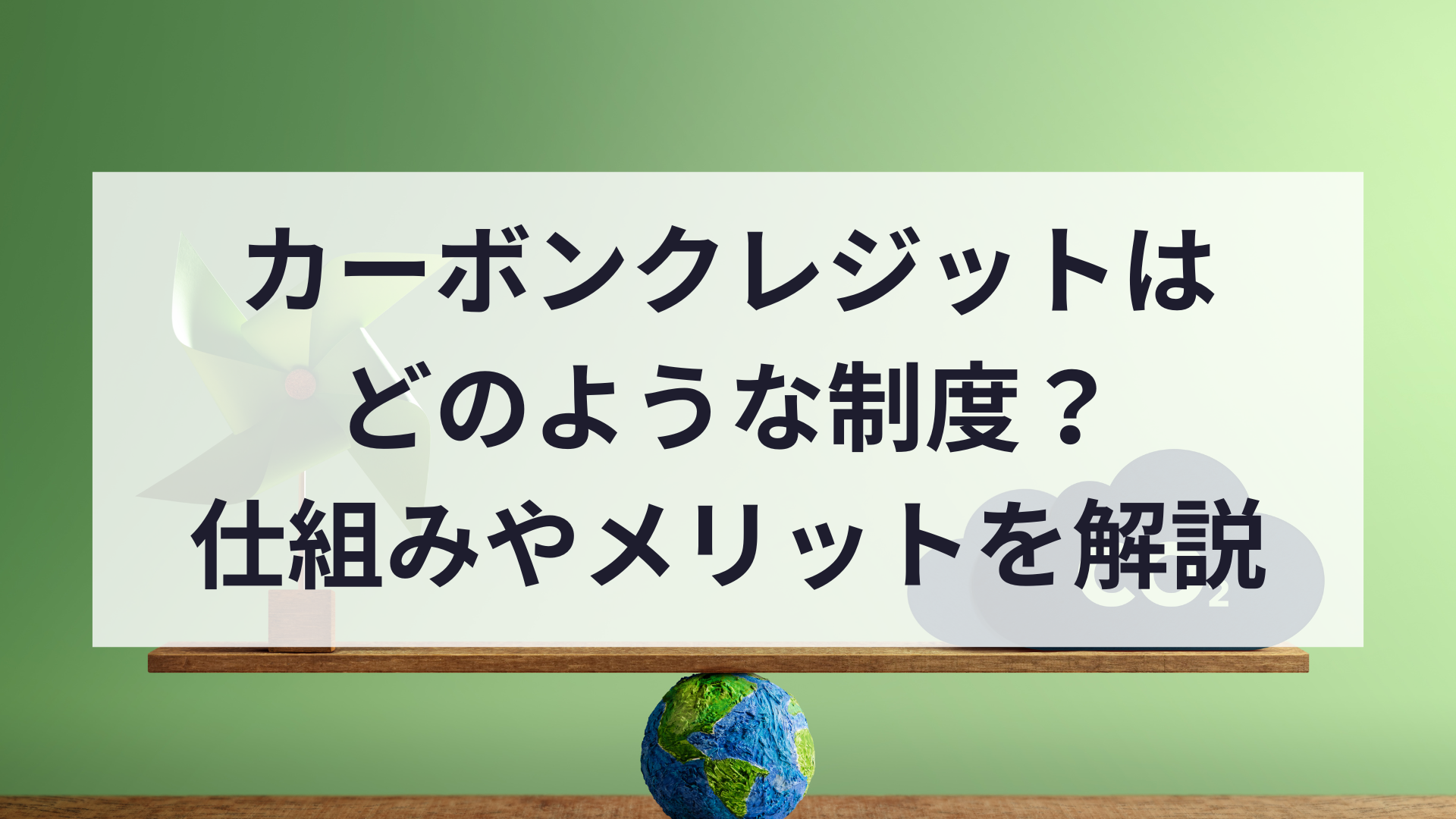日本の発電割合|再生可能エネルギーの発電方法・割合も紹介
2024.05.31
再生可能エネルギー
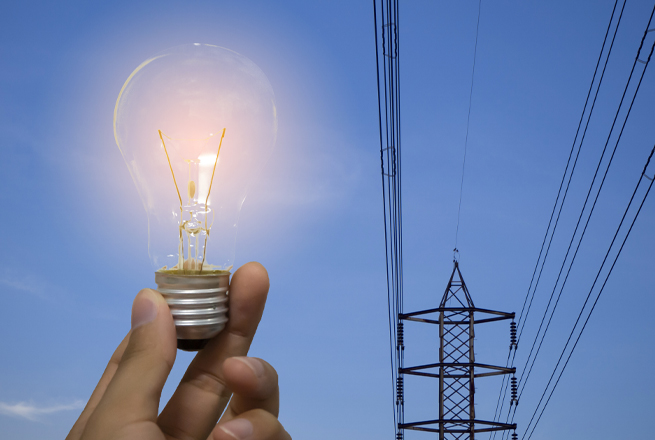
脱炭素化に向けた動きが世界的に加速している近年、化石燃料・エネルギーへの依存度が高い日本にとっては「非化石燃料・エネルギーによる発電」が喫緊の課題となっています。
しかし、日本の発電割合がどのようになっているのか、世界とどのような違いがあるのかを把握していない方も多くいるでしょう。
そこで今回は、日本の発電割合と世界の発電割合から、再生可能エネルギーの発電方法、再生可能エネルギーの発電割合を増やすための方法まで詳しく紹介します。
日本の発電割合
人々が普段使用する電力は、主に石炭・石油・天然ガス(LNG)などの「化石燃料」と、風力や水力をはじめとした「再生可能エネルギー」によって発電されています。
経済産業省資源エネルギー庁が公表した総合エネルギー統計によると、2022年度の日本における発電割合は下記の通りです。
| 発電割合(電源構成) | |
|---|---|
| 天然ガス | 33.8% |
| 石炭 | 30.8% |
| 石油 | 8.2% |
| 太陽光 | 9.2% |
| 水力 | 7.6% |
| 原子力 | 5.5% |
| バイオマス | 3.7% |
| 風力 | 0.9% |
| 地熱 | 0.3% |
出典:資源エネルギー庁「令和4年度(2022年度)における エネルギー需給実績(確報)」
日本国内のエネルギー供給は、化石燃料による発電、いわゆる火力発電が全体の72.8%を占めています。そして、再生可能エネルギーによる発電割合は21.7%、原子力発電・再生可能エネルギーを合わせた非化石燃料による発電割合は27.2%となっています。 日本は、電力供給の多くを火力発電に頼っていることが現状です。しかし、火力発電は化石燃料を燃焼する際、地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガスを排出することから、近年では再生可能エネルギーをはじめとした非化石燃料による発電への移行が課題となっています。世界の発電割合
日本は火力発電が主流で、再生可能エネルギーによる発電割合は全体の約20%となっていることが特徴です。しかし、国によっては原子力発電が主流だったり、再生可能エネルギーの電力比率が30%を超えていたりするなど、エネルギー事情はそれぞれ異なります。
そこで次に、アメリカやドイツをはじめとした世界の主要国における発電割合とその特徴を分かりやすく説明します。
アメリカ
資源エネルギー庁がサイト上で公表している資料によると、2021年度におけるアメリカの発電割合は下記の通りとなっています。
| 発電割合(電源構成) | |
|---|---|
| 天然ガス | 37.5% |
| 石炭 | 22.6% |
| 原子力 | 18.7% |
| 再生可能エネルギー(水力を除く) | 14.1% |
| 水力 | 6.0% |
| 石油・その他 | 1.1% |
アメリカでは、天然ガスによる発電が37.5%で主流となっており、石炭による発電が22.6%、石油・その他が1.1%と、日本と同様に電力供給の半分以上を火力発電に頼っています。一方で、非化石燃料である原子力発電の割合は比較的高く、2024年1月1日時点のアメリカにおける運転中の原子力発電所の基数は93基と世界で最も多いことも特徴です。
世界第2位のCO2排出国とされるアメリカは「2035年までに電力部門の脱炭素化を実現する」という目標を掲げ、再生可能エネルギーやクリーンエネルギー技術、さらに電気自動車などのさまざまな分野で多額のインフラ投資を行っています。ドイツ
2021年度におけるドイツの発電割合は、下記の通りです。
| 発電割合(電源構成) | |
|---|---|
| 再生可能エネルギー(水力を除く) | 36.3% |
| 石炭 | 30.4% |
| 天然ガス | 16.2% |
| 原子力 | 11.7% |
| 水力 | 3.3% |
| 石油・その他 | 2.1% |
ドイツは世界の主要国の中でも再生可能エネルギー導入が特に進んでおり、2023年の上半期には電力消費量の50%以上が自然エネルギー電力で供給されたことも分かっています。
出典:自然エネルギー財団「ドイツに見る原子力発電フェーズアウトの効果:自然エネルギー、蓄電池、水素を加速」
日本の再生可能エネルギーは太陽光の比率が大きい一方で、ドイツは風力やバイオマスが大きなシェアを得ていることも特徴です。「2030年までに国内電力消費量の80%を自然エネルギーで供給する」「2035年までには完全に脱炭素化する」という目標の達成に向けて、風力と太陽光を対象とした導入目標と優遇策も決定されました。イギリス
2021年度におけるイギリスの発電割合は、下記の通りです。
イギリスの発電割合は天然ガスが40.3%で最も高いものの、水力を除く再生可能エネルギーが37.9%となっているほか原子力による発電も多く、非化石燃料による発電の割合が化石燃料による発電を上回っています。
2021年には、「2035年までに温室効果ガスの排出量を1990年比で78%削減する」という目標を掲げ、島国の立地を活かした脱炭素化に積極的な姿勢を見せています。
| 発電割合(電源構成) | |
|---|---|
| 天然ガス | 40.3% |
| 再生可能エネルギー(水力を除く) | 37.9% |
| 原子力 | 14.9% |
| 石油・その他 | 2.8% |
| 石炭 | 2.4% |
| 水力 | 1.6% |
フランス
2021年度におけるフランスの発電割合は、下記の通りです。
日本と同様にエネルギー自給率が低いフランスでは、非化石燃料である原子力発電が主流となっています。また、再生可能エネルギーによる発電は全体の約22%を占めており、エネルギー政策においては特異な立場にある主要国と言えるでしょう。
フランスでは、2035年までに原子力発電の比率を50%に引き下げるとともに、ドイツやスペインから再エネ電力を輸入しながら再生可能エネルギーによる発電の割合増加を目指しています。
| 発電割合(電源構成) | |
|---|---|
| 原子力 | 68.9% |
| 再生可能エネルギー(水力を除く) | 11.2% |
| 水力 | 10.7% |
| 天然ガス | 6.1% |
| 石油・その他 | 1.6% |
| 石炭 | 1.4% |
中国
2021年度における中国の発電割合は、下記の通りです。
世界最大のCO2排出国とされる中国は、石炭による発電が全体の64.4%を占めていることが特徴です。しかし、次いで水力・再生可能エネルギー・原子力などの非化石燃料による発電の割合が大きいほか、再生可能エネルギーの導入実績においては世界トップを誇っています。
また、中国は太陽光発電事業が極めて盛んとなっており、国内外での圧倒的なシェアも獲得しています。こうした自国ならではの強みを活かし、「2060年までにカーボンニュートラルの実現」を宣言しました。
| 発電割合(電源構成) | |
|---|---|
| 石炭 | 64.4% |
| 水力 | 15.0% |
| 再生可能エネルギー(水力を除く) | 12.7% |
| 原子力 | 4.8% |
| 天然ガス | 2.8% |
| 石油・その他 | 0.3% |
再生可能エネルギーの発電方法
脱炭素化が世界的に注目されている近年、日本でも火力発電によるCO2排出量の削減に向けた取り組みが積極的に進められています。発電量のうち、再生可能エネルギーが占める割合も徐々に高まっているものの、依然として多くの課題が残っていることが実情です。
ここからは、各種再生可能エネルギーの概要・特徴や発電量全体に占める割合、さらに課題を分かりやすく説明します。国内における再生可能エネルギーの現状を理解するためにも、ぜひ参考にしてください。
太陽光発電
太陽光発電とは、シリコン半導体に光が当たると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを電気エネルギーに直接変換する発電方法です。
2022年度における日本の発電電力のうち、太陽光発電の割合は9.2%を占めています。
発電装置であるソーラーパネルは住宅の屋根にも設置でき、一時は多くの事業者や一般家庭での導入が進みました。しかし、資材コストや工事費、維持費の高騰などによって、普及の勢いが衰えているのが現状です。
出典:一般社団法人 太陽光発電協会「太陽光発電の現状と 自立化・主力化に向けた課題」
日本では、「2030年までに新築住宅の6割に10kW未満の住宅用太陽光を設置する」という目標を掲げています。昨今の原油輸入価格の高騰や円安によって太陽光発電が再度注目されはじめた状況ではあるものの、国の目標を達成するためには設備に適した土地や住宅の確保をはじめとしたさまざまな課題の解決が不可欠です。風力発電
風力発電とは、風の力を利用して「ブレード」と呼ばれる風車の羽を回転させることによって、風エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方法です。
2022年度における日本の発電電力のうち、風力発電の割合は0.9%と比較的低くなっています。
しかし、風力発電は環境負荷が少なく昼夜問わず発電できるほか、海に囲まれた日本にとっては変換効率の高い洋上発電が適していることから、2014年以降は導入件数が緩やかに増加しています。
風力発電の導入は今後も進むことが予測されているものの、天候や風力に発電量が左右される点や、洋上発電における漁業への影響・メンテナンスにかかる費用などの課題解決も同時に求められています。
水力発電
水力発電とは、高い位置から水が流れ落ちる際の「位置エネルギー」と呼ばれる力を利用し、水車やタービンを回して電気エネルギーをつくりだす発電方法です。
2022年度における日本の発電電力のうち水力発電の割合は7.6%と、再生可能エネルギーの中では太陽光発電に次いで高くなっています。
水力発電は日本の気候や風土に適していることが特徴ですが、ダムをはじめとした巨大な発電設備が必要となる大型水力発電所は、開発にともなう土地の確保が容易ではなく、増やすことが困難な状態です。
したがって、近年ではおおむね10,000kW以下の小水力発電が注目されています。小水力発電は、一般河川や農業用水などの小さな水の流れを利用することから、開発コストや環境負荷が少ないことが特徴です。
しかし、小水力発電の設置には水利権者の許可が不可欠で、許可を得るにあたって必要となる手続きには手間と時間がかかる点も難点です。小水力発電の普及に向けては、水利権者による許可を得るための手続きの簡素化や規制の緩和が課題となるでしょう。
地熱発電
地熱発電とは、地球内部の地熱を利用して蒸気を取り出し、その蒸気でタービンを回して電力を得る発電方法です。
2022年度における日本の発電電力のうち、地熱発電の割合は0.3%と低くなっています。
火山帯に位置する日本にとって、地熱発電は風土に適した発電方法であり安定的な供給が見込まれる一方で、発電量はそれほど多くありません。
また、地熱発電所の開発には多大なコストと時間がかかる点が最大の課題となっています。加えて、地熱発電の性質上、地熱発電として利用できるエリアは温泉や公園といった施設が点在する地域と重なることが多く、地元関係者との調整も求められています。
バイオマス発電
バイオマス発電とは、木材や植物、家畜排せつ物などの再生可能な生物資源(バイオマス)を燃料に、直接燃焼したりメタンガス化したりするなどして電力を得る発電方法です。
2022年度における日本の発電電力のうち、バイオマス発電の割合は3.7%を占めています。
バイオマス発電では廃棄物を再利用することから、環境改善および農林水産における自然循環・環境機能の維持増進・持続的発展に貢献できます。
一方で、バイオマス燃料となる生物資源は国内各地に分散しており、収集や運搬、管理にコストがかかる点や、バイオマス資源が限定的である点が課題です。
2021年度に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」では、「持続可能性の確保を前提に、各種政策を総動員しながらバイオマス燃料の安定供給の拡大と発電事業のコスト低減を図ることが必要」と表明されています。
再生可能エネルギーの発電割合を増やすことが求められている背景
前述の通り、再生可能エネルギーの導入は世界的に求められています。日本も当然例外ではなく、ニュースなどで一度は再生可能エネルギーという言葉を耳にしたことがあるという方がほとんどでしょう。
しかし、中には「なぜ再生可能エネルギーの発電割合を増やすことが求められているのか」がよく分かっていない方も多いのではないでしょうか。
再生可能エネルギーが必要とされる背景には、「地球温暖化の深刻化」と「低いエネルギー自給率」、さらに「パリ協定の採択」の3つのトピックが大きく関わってきます。ここからは、各トピックについて詳しく紹介します。
地球温暖化の深刻化
再生可能エネルギーが世界的に求められる最大の要因は、近年世界中で問題視されている「地球温暖化」です。温室効果ガスが主な原因となる地球温暖化は、気温上昇や異常気象を引き起こし、地球に存在するすべての生態系にさまざまな悪影響をもたらします。
これまで利用されてきた化石燃料をエネルギー源とした発電方法では、発電時にCO2をはじめとした温室効果ガスを排出するのに対し、再生可能エネルギーはほとんど排出しません。
電気は、人々の暮らしにとって欠かせないインフラです。地球温暖化対策・環境保全に向けては、エネルギー使用を控えるのではなく再生可能エネルギーの発電割合を増やす形で温室効果ガスの排出量を削減する必要があります。
低いエネルギー自給率
日本では、主要国の中でも再生可能エネルギーの発電割合を増やすことにより注力する必要があります。その理由としては、日本のエネルギー自給率の低さが挙げられます。
かつて日本は「天然資源によるエネルギー自給率」が高かったものの、人口増加や経済成長にともなうエネルギー消費量の増加によって自給率が大幅にダウンし、近年ではエネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っている状況です。
こうした状況では、国際情勢による貿易の滞りが国内のエネルギー供給に大きく影響するだけでなく、原油価格の高騰による「化石燃料調達に伴う資金流出」や「国民の経済的負担の増加」につながってしまいます。
しかし、日本で再生可能エネルギーの発電割合が増加すれば多くのエネルギー源を国内で調達でき、エネルギー供給や原油価格の高騰による影響も最小限に抑えられるようになります。
パリ協定の採択
日本を含む世界各国で再生可能エネルギーの導入が求められるもう1つの要因としては、「パリ協定の採択」が挙げられます。
パリ協定とは、気候変動問題に関する国際的な枠組みのことです。2015年にフランスで開催された「COP21」で採択され、翌年の2016年に発効した国際的な協定となります。
パリ協定では、「世界の平均気温上昇を、産業革命(18世紀半ば~19世紀)以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という目標が世界共通で掲げられました。
再生可能エネルギーの導入促進は、こうした「国際的・社会的・政治的な要請」という観点から見ても必要性の高い取り組みとなっています。
再生可能エネルギーの発電割合を増やすための「FIT・FIP制度」
エネルギー需要の高い日本では、温室効果ガスの排出量削減・エネルギー自給率の向上につながる再生可能エネルギーの導入が急務となっている一方で、導入には多大なコストがかかってしまうという難点もあります。
こうした難点をカバーしつつ、再生可能エネルギーの導入を促進するために打ち出された政策が、「FIT・FIP制度」です。最後に、FIT制度とFIP制度の概要と仕組みについて分かりやすく解説します。
FIT制度
FIT制度とは、「Feed-in Tariff(フィードインタリフ)制度」の略称であり、日本語では「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」と呼ばれています。事業者・個人が再生可能エネルギーで発電した電力を、電力会社が一定の期間にわたって一定の価格で買い取ることを保証する制度です。
再生可能エネルギーの導入におけるリスク低減・投資意欲の向上を主なねらいとしたFIT制度によって、制度開始後の2012~2013年は一般住宅における太陽光発電の導入量が大幅に増加しました。
しかし、FIT制度は一定期間の買取保証を提供する制度であり、期間満了後は買取価格が大幅に下がる点が課題となっています。
また、FIT制度と同時に開始された「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」では、FIT制度における再生可能エネルギーの電力買取費用を国民である一般電力消費者が負担する形となるため、反発の意見が多いことも実情です。
FIP制度
2022年4月には、新たにFIP制度「Feed-in Premium(フィードインプレミアム)制度」が導入されました。FIP制度とは、再生可能エネルギーの発電事業者に対して、発電電力の売電収入に加え「プレミアム」と呼ばれる一定の補助額を上乗せして交付するという制度です。
FIT制度との大きな違いは、「卸電力市場から売電先を自分で探す必要がある」「売電収入が一定ではなくなる」の2点が挙げられます。売電収入は、卸電力市場における売電価格に「基準価格-参照価格」で算出されたプレミアム単価が上乗せされた金額となり、電力需要に応じて価格が変わる点が特徴です。
長期的な収入の見通しが不明瞭となるため、事業リスクはFIT制度よりも大きくなりますが、FIP制度が普及すれば国民が支払う再エネ賦課金の負担をさらに抑えられる可能性があります。FIP制度における再生可能エネルギーの電力買取費用のうち、再エネ賦課金から支払われるのはプレミアム単価のみとなるためです。
なお、2024年現在、1,000kW以上の大規模な発電所はFIP制度の適用が義務付けられていますが、50kW以上1,000kW未満の発電所はFIT制度・FIP制度のいずれかを自由に選択できます。
まとめ
2022年度における日本のエネルギー供給は、化石燃料による発電(火力発電)が全体の72.8%を、再生可能エネルギーによる発電が21.7%を占めています。
再エネ比率が全体の1/3以上を占めている国もいくつか存在するなか、電力供給の多くを火力発電に、そしてエネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っている日本は、特に再生可能エネルギーの導入が重要視されています。
再生可能エネルギーは、企業だけでなく個人でも導入可能です。FIT制度やFIP制度も上手に活用しつつ、再生可能エネルギーを導入してみてはいかがでしょうか。

カーボンニュートラル実現へ向けた企業が取るべき具体的アクションとは?

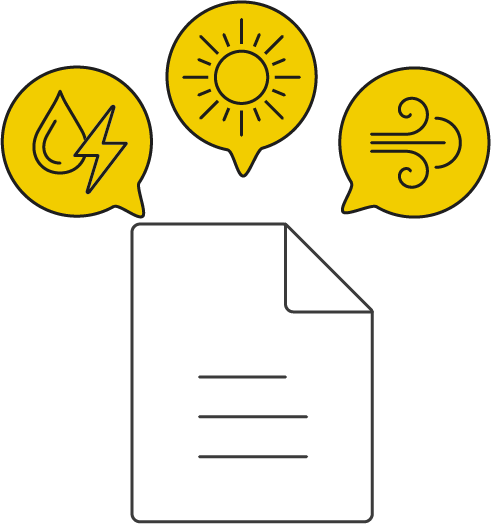 非化石証書購入代行サービス
非化石証書購入代行サービス
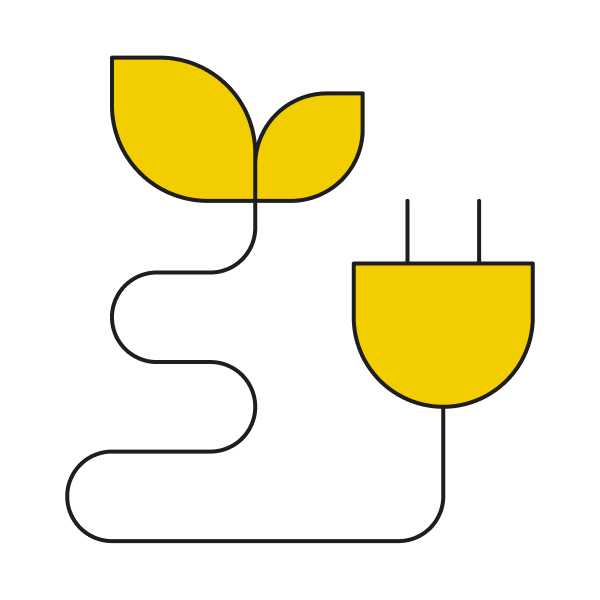 再エネ導入コンサルティング
再エネ導入コンサルティング
 電気料金比較サービス
電気料金比較サービス