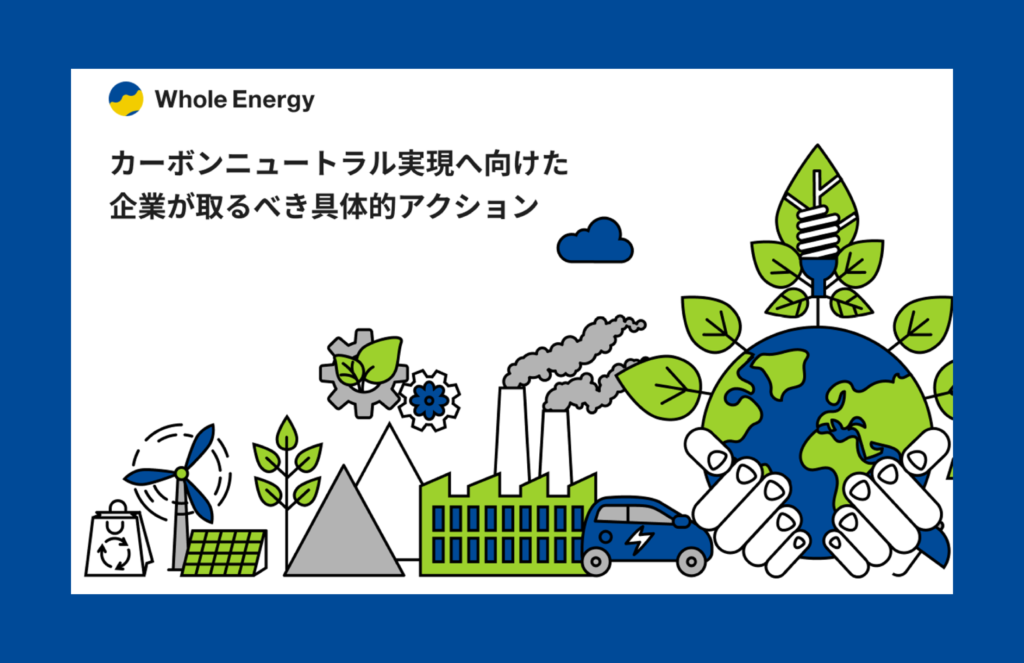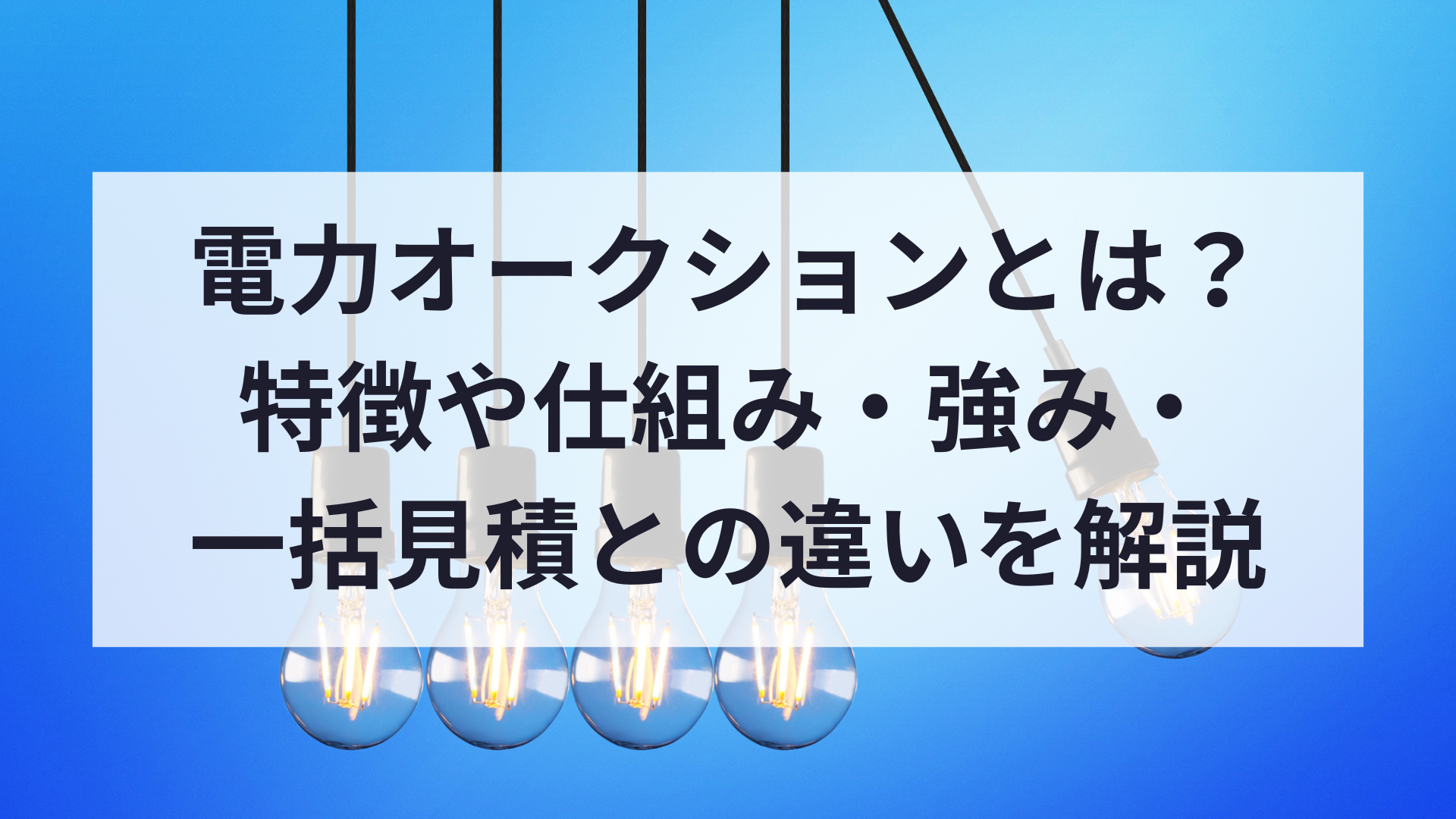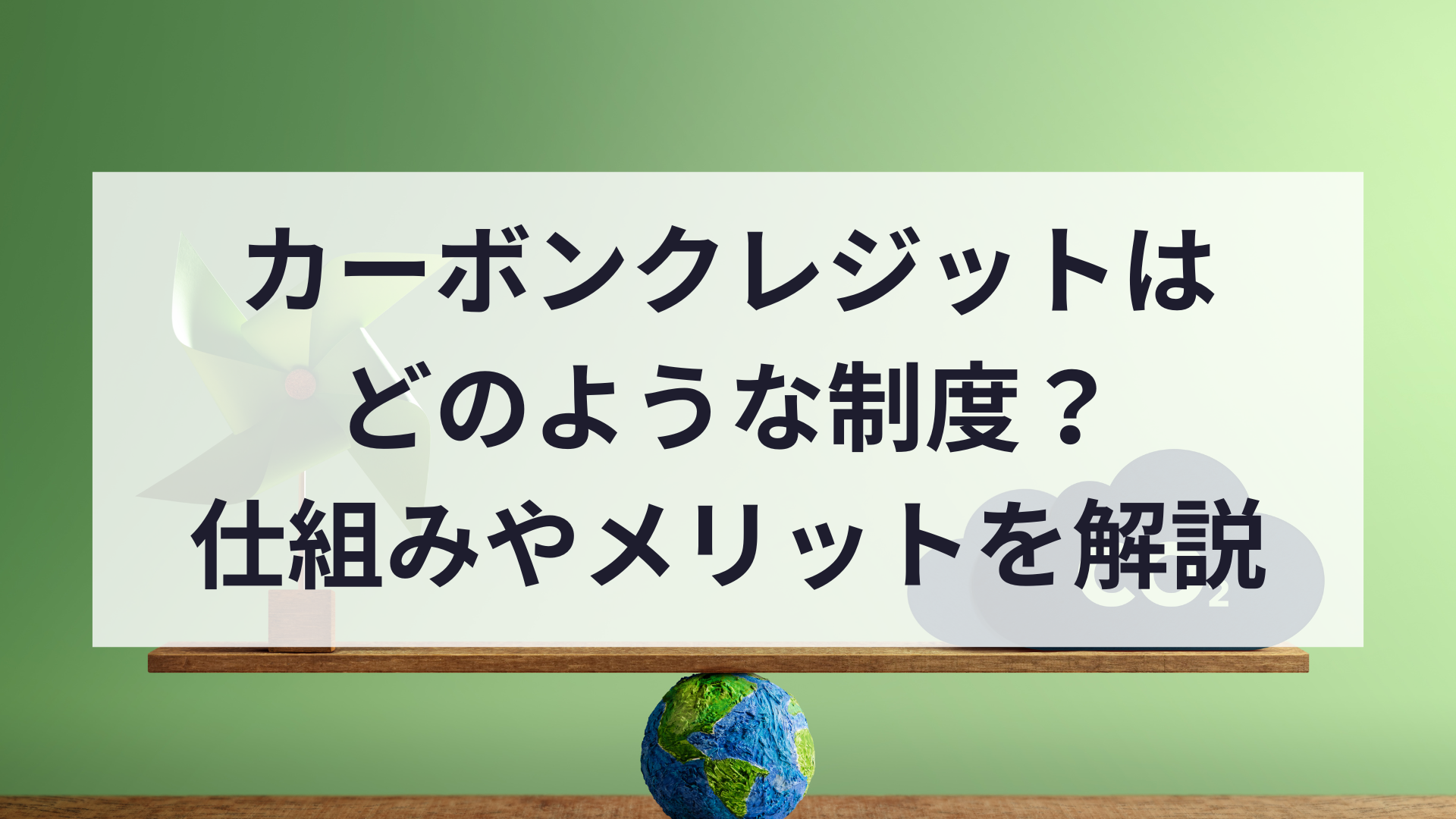企業のCO2削減目標とは?CO2削減が必要な理由・取り組み方・企業の目標

近年、CO2削減に取り組む企業は増加しています。生産活動を行う企業は、CO2削減目標を立てCO2削減について詳しく知る必要が出てきました。
本記事では、CO2削減が必要になった理由・企業にとってのメリット・具体的な取り組み方・各界の企業目標について解説します。
CO2削減をお考えの企業様は、ぜひ参考にしてください。
CO2削減目標とは?
世界が協力して温暖化を食い止めるため、具体的な数値を挙げてCO2削減の取り組みを始めたのが「CO2の削減目標」です。
各国の削減目標値は2015年のパリ協定に基づいて定められ、日本は温室効果ガスの排出量を2030年までに2013年比で−46%削減、2050年までに実質ゼロ(カーボンニュートラル)にすることを表明しています。
CO2削減の取り組みが必要となった世界的な背景
CO2削減に関しては各国が一致団結しています。それはなぜなのでしょうか?
地球温暖化に対する危機感
CO2やメタンなどの温室効果ガスは、熱を吸収して地球を温める役割がありますが、濃度が濃いと地表に熱がこもり気温が上昇し続けてしまいます。
すると極地の氷が溶けて海水が増え、様々な自然災害を引き起こします。
世界中で豪雨や干ばつ、山火事や異常気象が多発しており、誰もが「今までになかった変化」を体験し危機感を持っています。
パリ協定の採択
2015年にパリで開催された、国連気候変動枠組条約締結会議(通称COP)で合意された内容が「パリ協定」で、途上国含む全ての国が参加対象となりました。
パリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃に抑えることや、削減目標を5年ごとに提出・更新するなどを目標に掲げました。
国連によるSDGs目標の採択
2015年の国連サミットで採択された、持続可能な開発のための2030アジェンダに記載された国際目標を「SDGs」といいます。
17の具体的な目標の中で、「気候変動に具体的な対策を」というものがあります。
日本政府は、SDGs達成において優れた取り組みを行う企業や団体を表彰する制度を設け、民間での普及を後押ししています。
企業によるCO2削減が求められる背景
環境問題への取り組みを企業に求める傾向が強くなってきました。その背景には何があるのでしょうか。
日本政府によるCO2削減目標の発表
パリ協定において、日本は2050年までにカーボンニュートラルすることを宣言していますが、これは脱炭素社会の実現を意味しています。
その達成に向け政府は、再生可能エネルギー導入を促進する補助金制度や法整備を進めており、企業もCO2削減を含めた環境対策への取り組みに参加しやすくなりました。
カーボンプライシング・脱炭素対策の必要性
フィンランドやオランダではカーボンプライシング(炭素税)があり、CO2の排出量に応じて課税されています。
日本でも炭素税の導入議論が始まっており、将来的にCO2排出が企業コストの増大に繋がる可能性があります。そのため、省エネ型設備の導入や使用電力を再生可能エネルギーへ転換する施策が会計上のメリットとなるのです。
事業持続のためのリスク回避の必要性
世界的な異常気象が続くことは事業継続のリスクを増やします。
例えば、原材料の調達や確保が難しくなることや、原材料の値上がりの可能性があります。また、水害や山火事により製造拠点の稼働が止まったり、破壊されたりする可能性もあります。
環境対策に取り組むことは、中長期な事業継続のためにリスク回避となるのです。
企業がCO2削減で得られるメリット
CO2削減に取り込むことで企業が得られるメリットは年々増えており、経営戦略として組み込む価値が出てきています。
企業のイメージ・評価の向上
地球環境に配慮した姿勢を積極的に示すことで、市場や投資家・消費者から高い評価を得ることができます。また、金利優遇制度を利用できたり、資金調達において有利になったりします。
さらに、従業員のモチベーションアップや優秀な人材を獲得する上でも有効です。
エネルギーのコスト削減
日本はエネルギーを輸入に依存しているので、輸入価格が高騰すると国内の電気料金も値上がりします。
再生可能エネルギーは国内で電力を調達できるため、諸外国の事情に左右されません。長い目で見れば光熱費や燃料費の削減に繋がるでしょう。
企業活動の持続可能性の向上
経済活動をする上でエネルギーの調達は必要不可欠です。持続的かつ安定的に資源を調達することで、経営基盤が強くなり持続可能な企業活動ができるといっても過言ではないでしょう。
企業のCO2削減目標の事例5選
調査会社のブランド総合研究所が2022年7月に行った「第3回企業版SDGs調査2022」において、260社中上位5位にランクインした企業の取り組みを見てみましょう。
工場のCO2排出実質ゼロを目指す「トヨタ自動車」
SDGsの取り組みで最も評価が高かったのは、3年連続でトヨタ自動車でした。
同社では、車の生産工場を徹底的にスリム化し、工場で使う電力を再生可能エネルギーに切り替え、工場から排出するCO2をゼロにする活動を行っています。
店舗のCO2の排出総量ゼロを目指す「イオン」
2位のイオンは、2025年までにイオンモール全店舗の使用電力を100%再生可能エネルギーに切り替えることを表明しました。また、商品の製造からサプライチェーン全体での脱炭素化に取り組んでいます。
店舗と物流におけるCO2排出量実質ゼロを目指す「ユニクロ」
3位のユニクロは、2030年までに自社運営の店舗とオフィスのCO2排出量を2019年比で90%削減、使用電力を100%再生可能エネルギーに転換、商品製造におけるCO2排出量も2019年比で20%削減すると表明しました。
バリューチェーン全体でGHG排出量実質ゼロを目指す「サントリー」
サントリーは2050年までにバリューチェーン全体でCO2などの温室効果ガス(GHG)の排出量ゼロを目指しています。石油由来原料に比べCO2を約70%削減できるペットボトルリサイクル技術の開発に成功しています。
2030年までに全事業会社のCO2排出量実質ゼロを目指す「パナソニック」
パナソニックは事業活動において年間220万トンのCO2を排出していますが、同社の楠見CEOは2022年1月、2030年までに全事業会社のCO2排出量を実質ゼロにすると表明しました。
企業で取り組めるCO2削減方法
CO2削減は社会的意義があるだけでなく、経営上のメリットもあります。では具体的にどう取り組めば良いのでしょうか?
省エネのための対策をする
オフィスや工場で使う光熱設備を最新型に換えましょう。
最も電力を使う空調設備は、設定温度を調整したり、フィルターをこまめに掃除したりすれば一定の省エネ効果があり、屋外に遮熱塗料を塗ることで空調効率がアップします。
そのほかLED電球に替える、節水装置を付ける、ペーパーレス化を進めることも効果的です。
再生可能エネルギーの使用に変更する
太陽光・風力など自然由来の方法で発電し、CO2を排出しない電力を再生可能エネルギーといいます。再生可能エネルギーを扱う電力会社と契約することで、自社で使う電力をクリーン電力に変えることができます。
また、太陽光発電パネルを設置し自社で電力を生み出す企業も増えてきました。
ネガティブエミッションへの取り組み
大気中のCO2を除去・削減する技術を、ネガティブエミッションといいます。
植物はCO2を吸収し貯留(ちょりゅう)してくれますが、これに人為的な工程を加え吸収を加速させることで、効果的にCO2を削減できます。国は技術の実用化・ビジネス化にむけ議論しています。
カーボンオフセットへの取り組み
排出された温室効果ガスについて、どうしても削減できない分の全部もしくは一部を、植林・森林保護・クリーンエネルギー事業(排出権購入)などで埋め合わせをする考え方を、カーボン(=炭素)・オフセット(=埋め合わせる/相殺する)といいます。
これはあくまでも埋め合わせ対策としての使用が望ましいので、まずは自社でCO2削減への取り組みを行いましょう。
CO2削減に企業が取り組むうえでの課題
CO2削減に向けた取り組みを行う上で、注意しなければいけないこと、課題は何でしょうか?
CO2排出量の現状把握が難しい
これまでCO2排出量の開示を求められてこなかった業界では、CO2排出量の算定ノウハウがなく、自社の現状把握が難しい状況といえます。
CO2排出量の算定は環境省が提示していますが、計測が複雑で難しいため専門家の意見を必要とします。
震災後の化石燃料への依存度の高さ
2011年の東日本大震災後、全国の原子力発電所は停止しているため、現在の日本は石炭や石油といった化石燃料に依存している状態で、エネルギー利用の85%を占めています。
再生可能エネルギーへの切り替えコストの重み
国土の狭い日本は再生可能エネルギーの発電に適した土地が限られ、自然災害も多いため災害対策や修繕費用も必要なため、他のエネルギーよりも発電コストが高い状況です。
そこで国からの補助金や助成金を活用して切り替えコストを抑えましょう。
まとめ
CO2削減の取り組みは、企業の規模や業種に関わらず行うことができます。
社会の潮流としても事業を持続可能にしていく上でも重要度が増しており、対応を迫られる時代に入ったといえます。
ホールエナジーは、再エネ導入コンサルティングサービスとして、「何から始めていいか分からない」という企業様の対応を得意としています。
御社の現状や課題に合わせたご提案をさせていただきます。先ずはお気軽にご相談ください。
再エネ導入コンサルティングサービスの資料はこちら→https://www.whole-energy.co.jp/download/
参考記事
外務省 気候変動
外務省 SDGsとは?
経済産業省/産業技術環境局 ネガティブエミッション技術について


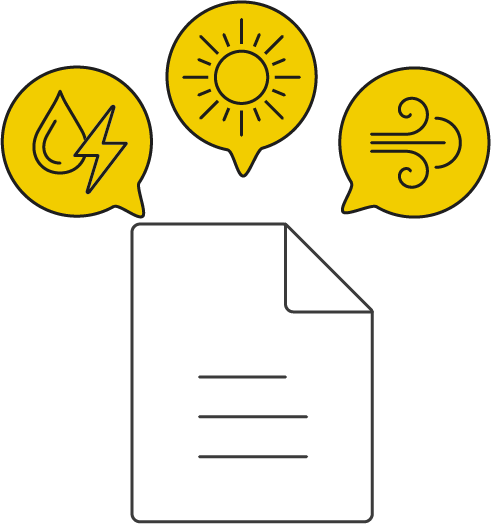 非化石証書購入代行サービス
非化石証書購入代行サービス
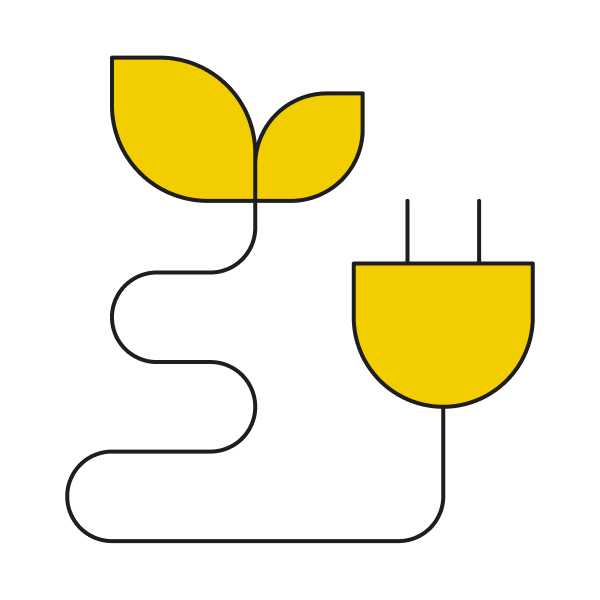 再エネ導入コンサルティング
再エネ導入コンサルティング
 電気料金比較サービス
電気料金比較サービス